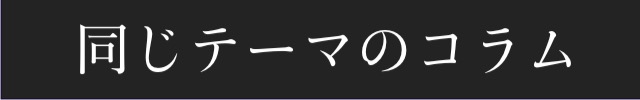がんで著名人が亡くなったニュースには、「早期発見のために検診を受けましょう」という決まり文句が付いてくる。
ではなぜ、毎年がん検診を受けていたのに、進行がんで見つかったという人が後を絶たないのだろう。
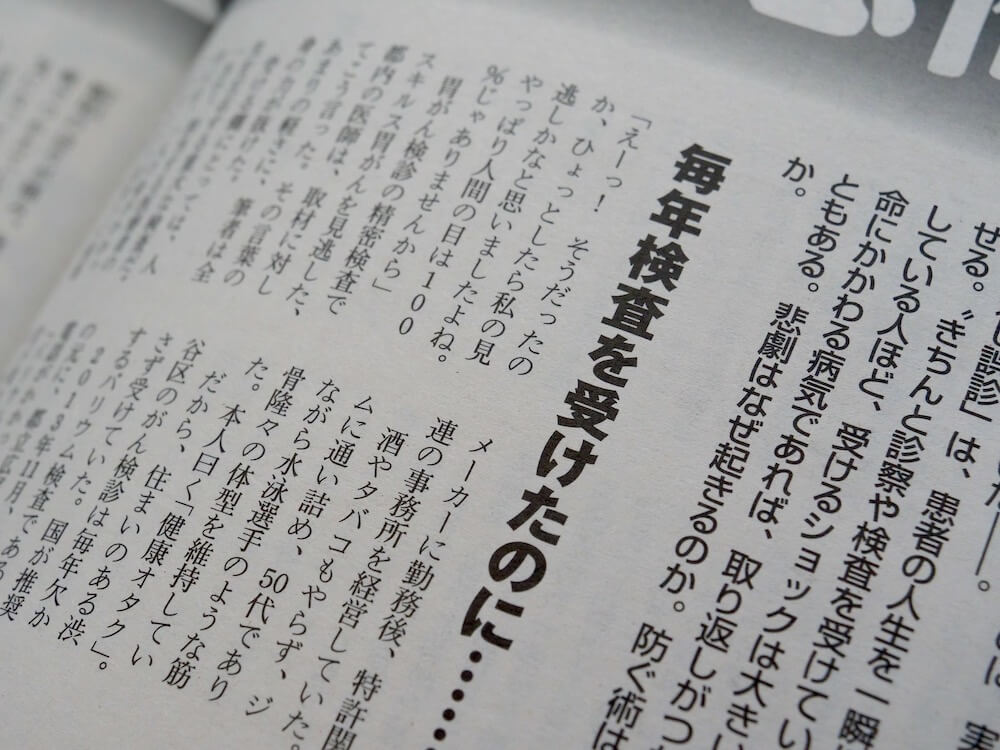
そんな疑問を抱いて、取材をしてみると、公的ながん検診として行われている「肺がんX線検査」(いわゆるレントゲン検診)では、約5割が進行がんで発見されていた。
胃がんのバリウム検査でも、約3割が進行がんで発見されている。
大腸がん検診の「便潜血法」は、世界的にスタンダードな手法だと、検診学者は胸を張る。しかし、よく調べてみると、アメリカでは、大腸がん検診として「便潜血法」以外にも、「内視鏡検査」や「CT」なども同時に採用されている。
これまで、日本のがん検診は、国立がん研究センターの旧検診研究部に在籍していた3人の検診学者によって、実質的に牛耳られてきた。 「がん検診の評価は、死亡率減少効果のみ」として、臨床医の意見に全く耳を貸そうとしてこなかったのだ。
「検診の先には、専門医による精密検査や治療がある」という現実を無視して、統計学や論文の評価に偏重している姿勢が、日本のがん検診を象徴している。
それに死亡率減少効果は、10年単位の追跡調査が必要となる。
その結果が判明した時には、社会構造とマッチしない、時代遅れのデータになっている場合がある。 日本がん検診は、臨床現場と乖離した、机上の空論になっていた。
「公的ながん検診には、科学的な証拠がある」という検診学者の主張も、疑ったほうがいい。 検診学者の目的は「集団での死亡率減少」でしかない。
「死亡率減少効果がある検診は、個人にとってもメリットがある」という言葉も、私は真に受けるべきではないと考えている。
ゲノムの時代にあって、集団予防接種のように全員一律に同じ検査を受けるなど、無駄な行為だろう。
また、検診学者たちは、日本がん検診が成果を上げていない現実に対して、結果責任をとっていない。
今回の特集では、公的ながん検診「肺がん、胃がん、大腸がん」に加えて、「肝臓がん、膵臓がん、前立腺がん」についても取り上げている。
各検診については、追って詳しくレポートしたい。
最近、週刊文春でがん検診の記事が出ていたが、私としてはその視点や方向性に違和感を抱いた。
どちらが正しいということではないが、一点だけはっきりさせたいのは、「過剰診断」という言葉は、がんを見逃された人にとっては虚しく響くということだ。