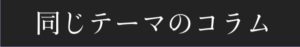現在、富岡町に24億円かけて救急医療を中心にした「ふたば医療センター」の建設が計画されているが、これは約5年で取り壊す予定だという。
大熊町に県立病院を新築する計画があるからだ。
これだけでも、「ふたば医療センター」は、莫大な無駄遣いと言えるが、さらに驚くべき二つの事実が取材で明らかになった。
まず最初は、東京電力・福島第一原発から22キロに位置する高野病院が「救急医療の体制を整備する」という提案を出しながら、福島県から黙殺されていた事だ。
繰り返しお伝えしているように、高野病院は第一原発から22キロに位置しながら、原発事故が起きてからも避難をせずに、入院患者を守り続けている。
2014年、事務長の高野己保さんは福島県の担当者に対して、高野病院を「救急医療」と「地域の拠点病院」として、機能強化を図るという計画案を示して協力を仰いだ。
「その頃、救急搬送の患者が急増して、対応が大変になっていました。双葉地域(広野町から双葉町まで)には、一時立ち入り住民や、原発関係、除染作業、土木工事など人たちが1万人以上増えた影響でしょう。 高野病院は、慢性期や精神科の患者が中心で、スタッフも最小限しかいません。本来は救急対応をする余裕は無かったのですが、院長は搬送を断らずに引き受けていたのです。ただ、このままでは無理が大きすぎるし、この地域としても救急医療のニーズが高いので、福島県に対して、高野病院に救急医療の機能を持たせる計画案を示しました」(高野己保事務長)

もし、高野病院が救急搬送を断れば、1時間以上かけて、いわき市の共立病院まで搬送しなければならない。
これでは、後遺症が残るおそれや命に関わる可能性もあるので、高野院長は極力引き受けていたのだ。
その結果、高野病院の救急搬送は、月平均15件になっていた。
多くは、夜間の搬送である。 震災以前は0〜3件だったので、高齢の高野院長には負担が大きかったはずだ。
こうしたデータを示して、救急体制を整える提案をした高野事務長に対して、福島県はこう答えた。
「民間病院だけを特別扱いすることはできない」
この主張は、公平性という観点では正論のようにも聞こえるが、本来は公立病院がやるべき事を民間の高野病院が担ってきた事実が抜け落ちている。
自らの責任を果たしていない役人には、羞恥心というものがないらしい。
本来は、地元紙が細かくチェックして、批判すべきことは批判することで是正されるはずだが、「県が民間病院を支援するのは異例」と書く始末だ。
双葉郡には診療を再開したクリニックもあるが、夜間の救急搬送に対応しているのは高野病院しかない。
「ふたば医療センター」でさえ、早くて平成30年4月が完成メド。
このような「箱モノ」を作らなくても、高野病院の機能強化で十分に対応可能なのだ。
さらに、もう一つの事実とは、富岡町に計画されている「ふたば医療センター」の、目と鼻の先にまだ十分に使用に耐えうる「医療施設」があることだ。
民間の今村病院は、築25年の6階建、ベッドは90床。震災後から閉鎖されているが、定期的なメンテナンスを行っているので、配管などの補修で使用可能な状態だという。
しかも、莫大な金額をかけて、二次除染まで完了している。
そこで「ふたば医療センター」の計画案がもちあがった際、今村病院の関係者が福島県に対して施設を提供する申し出を行ったが、答えは「NO」。
復興予算を獲得したので、とにかく使いたいらしい。
この今村病院は、今年3月に取り壊しされる予定だ。
環境省の予算が使えるリミットなのだという。解体費用は、約4億5千万円。
こんな馬鹿げたことが平気でまかり通っている「福島の現実」を放置してはならない。

苦々しい思いが募る一方の取材の中で、救われる場面もあった。
この日、遠く福岡市から高野病院の応援に駆けつけた医師の渡邊真里子さんは、不安を訴える入院患者の話を笑顔で受け止めていた。
これまで、高野病院とは全く無縁だったが、窮状をネットで知り、応援する決意を決めたと言う。
いま、高野病院を支援する輪は、南相馬の若手医師らによる情報発信で全国に広がっている。
クラウドファンディングには、予想を超える募金が集まり、3月までの常勤医も決まった。
そして、この6年間を杏林大学の外科チームやD-MATのメンバーたちが、立場を超えて高野病院を支えてきた。
まだ、日本も捨てたものではないと思う。

ただし、高野病院の存続をめぐる本質的な問題は、何も解決していない。
民間病院を特別扱いにはできない、という寝言を繰り返す福島県に対して、高野事務長は強い覚悟を私に明かした。
「これまでの福島県の話を考えると、高野病院を地域のために存続させるには、公的病院になるしか方法はありません。ですから、無償で県、もしくは広野町に譲渡するしか、方法はないと決意しました」
亡くなる当日まで患者を診察していた高野英男医師は、この状況についてなんと言うだろう。 そして、私たちは傍観するだけでいいのだろうか?