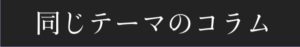演出家・きたむらけんじ氏の「幸福な職場」という舞台が、
東京・世田谷パブリックシアターで行われていた。
学校で使われている黒板用のチョークを製造する会社が、知的障害を持つ少女を従業員として受け入れる物語だ。
足手まといになるだろうと考えて、拒絶する従業員。仕事をする能力はないだろうと考える経営者。
彼らの予想は見事に裏切られる。
職場に人を思いやる優しさが広がり、チョークの製造を効率的に変えていくのだ。
殺伐とした現代においては、この物語は理想を描いたファンタジーだと思うかもしれない。
だが、これは全従業員81人中60人の知的障がい者が働いている日本理化学工業をモデルに、きたむら氏が脚本化した実話だ。
故・高野英男先生が急逝して、存続の危機にたつ福島の高野病院。入院患者100人のうち、半数は精神障害の患者である。
私は取材をしていて、なぜ地元住民から存続を求める声が上からないのか、不思議に感じていたら、「あそこは精神病院だから」という話を聞いた。
精神障害の患者と、前述の知的障害者は、もちろん異なる存在だ。
だか、彼らに向ける社会の視線は、同質であると感じてならない。
彼らの実像を知らないままに、遠ざけているからだ。
高野病院の昼下がり、受付に入院している精神障害の患者たちが一人づつ立ち寄り、職員と言葉を交わす。
一見すると無表情なのだが、内面に豊かな感性を宿している人もいるという。
初めて高野病院を訪れた時、受付の事務スタッフ、看護師、介護士に、穏やかで優しい雰囲気が漂っていることに私は内心驚いた。
いま、福島県外に避難している精神障害の患者は、103名。
その人たちの希望を聞いたところ(福島県のマッチング事業)、
H28年7月末まで累計52名の精神障害の患者が、高野病院への転院を希望していた。
福島県の双葉郡で、精神障害の患者が入院できる病院は、高野病院しかないこともあって、彼らは今も故郷から離れて生活している。
高野病院を必死で守ろうとしている人々は、日本の社会が失いかけている優しさと、人間の尊厳を取り戻そうとしているのだろう。
まだ、この国には希望はある。