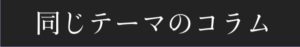取材中には、思わぬ瞬間が訪れる時がある。
王様のような顔をした猫が、いつの間にか私の背後にいた。
彼がじっと見つめているのは、デジタル一眼カメラGH4のモニター画面。
そこに写っていたのは、末期がん患者の飼い主だった─
これは、群馬県の緩和ケア診療所「いっぽ」の訪問看護に同行取材した際の一コマ。 この患者は、自宅で猫たちに囲まれて一人暮らしをしていた。
がんの種類にもよるが、抗がん剤治療による効果は、いつまでも持続するわけではない。 命の残り時間が迫っている現実に、向き合う時が必ずくる。
最後の瞬間まで治療を続けたい、という末期がん患者は少なくないが、「治療そのものが目的化」してしまっていることに、患者本人や家族が気づいていないこともある。
最後まで積極的な治療を続けることは、日常生活が困難になる程に身体や心が痛めつけられ、自分らしい時間を過ごすことを「諦める」ことにつながるのだ。

一般的に考えると、末期がん患者が一人で自宅で過ごすのは無謀と思われるかもしれないが、そうではない。
「緩和ケア診療所・いっぽ」では、看護師が定期的に訪問することによって、一人暮らしの末期がん患者の心を支え、猫たちとの生活を実現している。
患者は、王様のような顔の猫に「見守られている」と私は感じた。
それは幸福な時間だと思う。
抗がん剤治療をやめることは、決して「諦め」ではない。
現実と向き合い、残された時間を自分らしく生きるという「選択」の一つだ。 その時、心を支えるのが「緩和ケア」だ。
残り時間をどう生きるか? それは末期がん患者だけでなく、私たちに共通したテーマでもある。